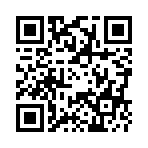2010年01月07日
ルーツ、アイデンティティを考え直す
この時代様々な業界で将来への懸念が生まれているんだなぁとあらためて感じる事があった。今日訪問したお客様での話。そこは寺。寺社仏閣業界というか、宗教業界というか、少なくとも僧侶だけに限定した話ではないと思うんだけど、要約するとこんな話。
檀家さんの寺離れが顕著になって来ている。
家族葬等新しい形態の葬送を選び、寺・僧侶不在の葬送が増えている。
残された遺族がいるのに、故人(家としての)の墓を持とうとせず、永代供養を希望する方が増えている。
首都圏や横浜等では、実に3割程度の方々は寺・僧侶不在の葬送をなさっているらしい。
核家族から、個家族(家族の中の個)、そしていよいよ孤家族(老齢者を中心に)の時代になってきた。
祖先を敬い、家系、血脈を大切にすると云う気持ちがどんどん希薄になっていくっている。
言いたかないが、多分に今の時代の経済状況も影響している。
こんな寂しくなってしまうような話を、もっともっともっと沢山言っていた。
今まで檀家制度に甘んじてきた寺業界そのものへの批判を込めて、自戒の念とともに憂えながらの業界トーク。各地域における寺社仏閣の役割の見直しと、その存在価値向上の努力を寺社(の業界)として取り組んでいかなければと云う前向きな想いがそこにある様子。今のお寺が、死者を葬る手段としてのみ存在するんだったら、前述の状況が進むほどにお寺はなくなっちゃうかもしれない。昔は近所の神社や寺で遊ぶ子供達の姿や、晦日の鐘突き、熱心な方は朝参りもしていたんだろう。今のこの状況はもはや信仰以前の問題だと嘆いておられた。
私がこの住職を大好きなのは、それらの話を過去の歴史や今を生きる檀家さん方のせいには決してしていないところ。自分たちの努力で「この町にはこんな素晴らしい寺があるんだ」と想ってもらえる寺作りを、自らがしていかなければいけないと言っておられるところ。正直言うと世の中には「こんなお坊さんに頼みたくないな」と思わせる僧侶の方も多々いる中で、とても真面目な取り組みをなさっているこの方が大好きだ。
'45の敗戦後、教育と文化の歴史を一旦ぶった切られてから、或いはその頃の教育をどストライクで受けてきた世代(まさにこの住職がその世代)以降、前述の傾向が強いというような事も言っていた。勝った国だからといって負けた国の文化と教育を変え、その結果国家の将来を変えてしまう行為はやはり罪深い。
清水もつカレー総研の野口さんが口を酸っぱくして言い続けている「つがりなおし」と云う言葉がある。地域再生のキーワードとして素晴らしい響きを持っている言葉だと想っていたけど、実は人として、日本人として、親祖先との「つながりなおし」を意識しなければいけない時に来てしまっているんだなァと強く感じた。
今、私は出勤前に義父の仏壇に手を合わせている。
私の義母と両親は今のところ健在だが、弔う時には気持ちがしっかりと繋がりあった状態で葬送したい。
いずれ子供達が我々夫婦を弔ってくれる時が来るならば、やはり繋がった状態で見送られたい。
そうすれば我々が存在しなくとも、彼らの記憶の中で、いくらでも導いていくことが出来るような気がしているんだ。だからそのためにも、生ある今を一生懸命生きなければいけないんだと思う。
あんしんボスのONとOFF!
こういう話はついつい熱が入ってしまうあんしんボス
年始回りのつもりがついつい1時間も話し込んじゃったよ、その寺で。ウチはそこの檀家ではないんだけどね。
by 影山 @ あんしんビジネスサポート株式会社 @ 富士市厚原
檀家さんの寺離れが顕著になって来ている。
家族葬等新しい形態の葬送を選び、寺・僧侶不在の葬送が増えている。
残された遺族がいるのに、故人(家としての)の墓を持とうとせず、永代供養を希望する方が増えている。
首都圏や横浜等では、実に3割程度の方々は寺・僧侶不在の葬送をなさっているらしい。
核家族から、個家族(家族の中の個)、そしていよいよ孤家族(老齢者を中心に)の時代になってきた。
祖先を敬い、家系、血脈を大切にすると云う気持ちがどんどん希薄になっていくっている。
言いたかないが、多分に今の時代の経済状況も影響している。
こんな寂しくなってしまうような話を、もっともっともっと沢山言っていた。
今まで檀家制度に甘んじてきた寺業界そのものへの批判を込めて、自戒の念とともに憂えながらの業界トーク。各地域における寺社仏閣の役割の見直しと、その存在価値向上の努力を寺社(の業界)として取り組んでいかなければと云う前向きな想いがそこにある様子。今のお寺が、死者を葬る手段としてのみ存在するんだったら、前述の状況が進むほどにお寺はなくなっちゃうかもしれない。昔は近所の神社や寺で遊ぶ子供達の姿や、晦日の鐘突き、熱心な方は朝参りもしていたんだろう。今のこの状況はもはや信仰以前の問題だと嘆いておられた。
私がこの住職を大好きなのは、それらの話を過去の歴史や今を生きる檀家さん方のせいには決してしていないところ。自分たちの努力で「この町にはこんな素晴らしい寺があるんだ」と想ってもらえる寺作りを、自らがしていかなければいけないと言っておられるところ。正直言うと世の中には「こんなお坊さんに頼みたくないな」と思わせる僧侶の方も多々いる中で、とても真面目な取り組みをなさっているこの方が大好きだ。
'45の敗戦後、教育と文化の歴史を一旦ぶった切られてから、或いはその頃の教育をどストライクで受けてきた世代(まさにこの住職がその世代)以降、前述の傾向が強いというような事も言っていた。勝った国だからといって負けた国の文化と教育を変え、その結果国家の将来を変えてしまう行為はやはり罪深い。
清水もつカレー総研の野口さんが口を酸っぱくして言い続けている「つがりなおし」と云う言葉がある。地域再生のキーワードとして素晴らしい響きを持っている言葉だと想っていたけど、実は人として、日本人として、親祖先との「つながりなおし」を意識しなければいけない時に来てしまっているんだなァと強く感じた。
今、私は出勤前に義父の仏壇に手を合わせている。
私の義母と両親は今のところ健在だが、弔う時には気持ちがしっかりと繋がりあった状態で葬送したい。
いずれ子供達が我々夫婦を弔ってくれる時が来るならば、やはり繋がった状態で見送られたい。
そうすれば我々が存在しなくとも、彼らの記憶の中で、いくらでも導いていくことが出来るような気がしているんだ。だからそのためにも、生ある今を一生懸命生きなければいけないんだと思う。
あんしんボスのONとOFF!
こういう話はついつい熱が入ってしまうあんしんボス
年始回りのつもりがついつい1時間も話し込んじゃったよ、その寺で。ウチはそこの檀家ではないんだけどね。
by 影山 @ あんしんビジネスサポート株式会社 @ 富士市厚原